|
|
「経営研究所での講演内容」 瀬戸 欣哉 (住商グレンジャー株式会社 代表取締役社長)
日本のB2Beコマースの現状 ―アメリカ・グレンジャー社との提携から―はじめに私が、アメリカのビジネススクールに通っていたのは、1996年のことである。この年は、アメリカの「インターネット元年」と呼ばれている年であり、96年にビジネススクールを卒業した私の同級生たちは、98年〜99年になるとほぼ100%がコンサルタント会社や投資銀行、eコマースベンチャーなど、何らかの形でeコマースビジネスに関わる就職をしていた。 1999年は、日本の総合商社がB2Bに参入しようとしていた頃で、「B2B元年」とも言われる年である。各社がさまざまなマーケットプレイスを立ち上げようと試み、そのなかで、私は鉄のマーケットプレイスの立ち上げプロジェクトに参加していた。 こうした経験から、現在のビジネスを提案し、立ち上げていくことになるのだが、本日の報告では、現在のビジネスを提案するに至った背景、現在のB2Beコマースの現状と問題点についてお話する。 1. インターネットの特性を生かしたビジネスの提案アメリカのビジネススクールに在籍していた当時、後にeコマースビジネスに関わることになる友達たちとよく話をし、そのときに、ほぼ皆が同意した意見は、「インターネットのビジネスは、今のビジネスをeに置き換えるだけではうまくいかない。何らかの形で、インターネットの特性を生かしたビジネスにしなければいけない」ということだった。 このことについて、私なりに考えた結論が、「インターネットの特性=検索」であった。インターネットを使う人が一番便利だと思うのは、検索で簡単に情報を探せることだと思う。この機能こそが、インターネットの最も基本的な機能だろうと考えた。インターネットを使ってビジネスをする以上、この検索能力を使わないと意味が無いと考えた。そこで、検索とは何かということを考えてみた。検索とは、知識の少ない人が、広い範囲から探し出してくることであると定義できる。この定義からすると、商社が普段扱っている「主資材」というものは、検索を必要としない商品であることが分かった。 「主資材」という商品は、誰がどんなことについて知っているかという知識を有機的に持っている人たちが多く、そうした人たちは、インターネットを使った検索など必要としない。検索は標準化された広い情報のなかから調べるのに適しているが、それに向いているのは間接資材であった。 「間接資材」とは、「最終製品にならないすべてのもの」と定義される。たとえば、メガネを作ることを考えた場合、ガラスやチタンフレームやネジは直接資材であるが、フレームを曲げるときに使うプライヤーや、ガラスの研磨用砥石、軍手や工場で使う蛍光灯といったものは、すべて間接資材になる。 この例から分かるように、間接資材は膨大な数になり、日本だけで600万種類が出回っているといわれている。直接資材として通常使われるのが数千〜1万種類といわれ、なおかつ、それについて購買担当の人が良く知っている。一方、間接資材は購入金額では全体の20%ほどでしかないが、購入に費やす総時間の80%を使って購入している。時間がかかる理由は、探すのに手間がかかるからである。こうしたポイントから、インターネットの検索機能が間接資材ビジネスに向いているのではないかと考えた。 たまたま、アメリカのグレンジャーという会社が、同様のビジネスをインターネット上で1996年から展開し、非常に急成長していた。こうしたビジネスが、日本でやれないものかと思い、ビジネスを提案していくきっかけになった。 2.住商グレンジャーの起業と現状当時、私は住友商事のマーケットプレイスを立ち上げる仕事のプロジェクトリーダーをしていた。しかし一方で、上述のビジネスをやってみたいという気持ちが非常に強かった。そのため、1999年の秋にアメリカのグレンジャー社 に、このビジネスを立ち上げるためのフィージビリティ・スタディを申し入れた。グレンジャーのほうも積極的で、その年の暮れにはフィージビリティ・スタディの契約を結ぶことができた。 フィージビリティ・スタディを始めて2〜3ヵ月で分かったことは、実際に会社を始めてみなければ、何も分からないということだった。そこで、2000年10月に住商が51%、グレンジャー49%の出資比率で資本金1億円の会社を設立した。 この設立の時点までに、私はいろいろなeコマースの会社を商社の人間としてみてきていた。たくさんの失敗例も見てきた。失敗した企業には共通するのは、EコマースやITビジネスというとスピードが大切であり、そのためには、すぐに作らなければいけないと考えて、いきなり集めた資金を全部つぎ込んでコマーシャルプラントを作ってしまう点だった。そして、不具合が出て、改良が必要になったときには、お金が足りなくなってしまって、結局、失敗するというパターンが多かった。 そこで、私がグレンジャーに対して提案したのは、とりあえずパイロットプラントを作ろうということだった。パイロットプラントを1年動かしてみて、不具合を見つけたり、どこをアップスケールし、どこをダウンスケールするかをみつけて、そうした用件定義がすんだ後に、コマーシャルプラントを作ることにした。 パイロットプラントの間の1年間は、ASPを使用するとともに、お客さんも40社に限定していた。B2Bビジネスは、単に商売ができるだけではなく、運んだり、在庫したり、決済したりするところに難しさがある。この部分をすべてシステム化するとまたお金がかかるので、最初は人手でやっていた。いわば紙芝居のようなeコマースであったが、このパイロット期間を経て、自分たちの新しいコマーシャルプラントを立ち上げたのが、去年の11月である。現在では、顧客数が1万2000社で、今月の売り上げは1億円を越すと見込まれ、今年中にはペイラインを超えると考えている。 また、パイロット期間が終了した時点で、出資の面も変化した。それまでの住友商事、グレンジャーの2社に加え、三井物産、アメリカのベンチャーキャピタルのウィットインベストメント、日本のベンチャーキャピタルのUFJキャピタル、新規事業投資、SMBCキャピタルなどが出資し、資本金が19.5億円になった。 以上のように、今の会社を設立し現在に至っているわけだが、この間に、私は日本のB2Beコマースビジネスの黎明期からの成り行きを体験することとなった。次に、日本のB2Beコマースビジネスの経緯についてお話したいと思う。 1)グレンジャー社 70年前にシカゴで創業。今から25年前に間接資材のB2Bビジネスを始める。業界の抵抗を受けながらも、水平的にいろいろな製品をカタログに、ワンプライスで載せるカタログ販売を始めた。現在年商6000億円で最大手企業の1つである。 3.日本におけるB2Beコマースの展開と現状(1)B2Beコマースとは B2BとB2Cの違いは図に示したとおりである。また、eコマースを定義するなら、「インターネット上で売買契約がなされるもの」といってよいだろう。 B2BとB2Cのコンセプト上の最も大きな違いは、B2Cが一物一価であるのに対し、B2Bは一物多価が中心であるという点だと思う。この点が、B2B特有の難しさを生んだり、B2Bビジネス自体の成長を阻害してきたといえる。私自身は、将来的には、B2Bも一物一価に向かっていくのではないかと考えている。一物多価を前提にした既存のB2Bは絶滅の危機にあると考えてよいだろう。
(2)1999年 黒船襲来 −総合商社の危機− なぜ、Eコマースが成長すると、なぜ仲介業者が要らなくなると考えたのか。それは、当時、以下の三つの考えが、eコマースによってもたらされるというコンセンサスがあったためである。 1. Rich & Reach これは、情報の質と量の反比例関係の制約が無くなるという考え方である。商社のビジネスは、昔の回船問屋と変わらないもので、北で油が高ければ油を持って行き、南で魚が高ければ魚を持っていくというのがビジネスである。それぞれの地域で、情報が不均衡であるために価格に高低がある。また、ある地域や商品に対して非常に豊富な情報を持っている人がいたとしても、その人は他の地域や他の商品に対して情報を持っているわけではない。つまり、情報の豊富さと情報の広さには反比例の関係があるのだ。この制約の上に成り立っていたのが商社のビジネスである。ところが、インターネットを使って、誰でもが安価に情報を手に入れてしまうなら、Rich & Reachの制約の上に成り立っていた商社は必要なくなってしまう。これがいわゆる「中抜き論」であり、最も商社が恐れる事態である。 2. Buyercentric model インターネットの時代になると、バイヤーの力が非常に強くなる。C2CやB2Cのモデルやフリーマーケットに見られるリバースオークションでとことん安く買うモデルが成立したことからも分かるように、力関係が基本的に売り手から買い手に移ってきている。商社は、そもそも売り手にくっついてきたのであって、買い手やユーザーを見ては来なかった。ところが、バイヤーセントリックになってくるという流れが生まれてきたので、ここでも大きな危機感を持つことになった。 2. One to One One to Oneビジネスとは、マーケティング対象の最小単位が小さくなることを意味している。商社は基本的にエンドユーザーとのつながりを持っていない。そのことから、One to Oneには対応できない。 こうした点から、仲介業者が不要になるのではないかと考えた。そこで、不要とされる前に、自ら新しいマーケットプレイスを構築する道を選ぶことで、将来を何とかしようとする発想が商社のなかから生まれてきた。 この時点で、アメリカの鉄鋼取引では、メタルサイトとeスチールの2社が急成長していた。こうしたサイトを商社自身で取り込んでしまわないと、自分たちの商売がなくなってしまうと考えたのだ。商社は、マーケットプレイスをやっておかないと、自分たちの存在意義がなくなってしまうというリアクティブな発想から動きだしたのである。 (3)商社の対応策 −3つのモデルの創出− 1つ目は、Virtual storeであり、B2Cと同じスタイルである。これは、One to Manyの関係でビジネスを成り立たせようとしている。いまある流通手段(店舗、通販、fax通販など)に加え、新たにインターネットでも売り出しましょうというモデルである。 2つ目は、Market Placeである。これは商社が恐れていたものであるがゆえに、自分でやろうとしたものである。このモデルは、Many to Manyを対象にしている。商社としては、新市場の形成と業界インフラの建設、そして、そこで主導権を握ることを狙っていた。 3つ目は、Procurement siteである。これは、買い手側の業務効率化を目指して作ったものである。当時は、アリバやコマースワンのソフトを使ってMany to Oneの形態を作ることが主流になるだろうとみなされていた。 当時は、これら3つのモデルが考案されたが、最終的にはMarket Placeモデルに集約されていくだろうと考えている人が多かった。なぜなら、Virtual storeやProcurement siteは、売り手、買い手のどちらかがOneであるために、選択肢が少ないモデルになってしまうからだ。商社がMarket Placeに予想していたことは、Many to Manyで、売り手、買い手が複数の相手と好きなように取引ができるという、ハッピーな関係が築けるモデルだという点にあった。 (4)3つのモデルの総括 1. Virtual storeモデルの総括 Virtual storeの定義は、「一対多数でタイトルを取ってのインターネット上での販売」である。この「一」の側が、売り方や運び方などを標準化することで成立しているモデルである。このモデルは、メーカーが既存の流通ルートに追加する形で設立するケースが多い。しかし、既存の販売で代理店などを起用している場合、反発を招くので、実際の販売にはあまり力を入れていない場合が多い。 このモデルについて評価すると、基本的には既存の販売流通に、新たにプラスαの流通手段としてサービスを向上させたという意味で、一定の成功を収めたといえる。ある程度パターン化された質問に対して、ルール化された解答を用意したり、在庫確認がしやすくなったなど、サービス向上の面ではうまくいったし、サプライヤーのコスト削減という面でも非常にうまく使われたといえる。 Virtual storeの機能で、最も多く利用されているのは、在庫確認である。インターネット上で確認をし、商売は電話やファックスで行うというパターンは非常に多い。 Virtual storeモデルにおいては、B2B特有の一物多価の問題が大きな障害となっている。一物多価ゆえに、インターネット上に本当の売れる値段を表示することができないのである。たとえば、ある会社が同じ製品を、A社B社C社に別々の価格で売っていたとする。そのときに、インターネット上で表示できる値段は、一番高く売っている値段にせざるを得ない。本当なら一番安い値段を表示したいのであるが、それを表示してしまうと、今まで高く買わされていた会社が反発する。この問題がある限り、インターネットを使ったB2Bでは、魅力的な値段が表示されることはない。売る会社ごとに違う値段を表示していくことができれば一番いいのだが、それではデータベースが莫大になり、管理することが難しくなるし、高いコストになる。 ユーザーはインターネットだとコストがかからないのだから、その分安くなるだろうと期待しているが、こうしたB2Bでは、むしろ値上げになってしまう。そのため、売買の手段としては使えなくなる。インターネット上に表示される値段は、「皆さんにはこの値段で売っています。でも、あなたには2割引で売ります」という、見せ金的なものに過ぎなくなってしまうのだ。 今後のVirtual storeの展望としては、サプライヤーが便利になるという省力化の手段として広がっていくのではないかと思う。しかし、メーカー自身が、代理店や販売店を使っている場合には導入が難しい。また、お客さんによって売値が異なるという一物多価の問題がある限り、このモデルの利用には限界がある。 2. Market Placeモデルの総括 Market Placeの定義は、「多対多でタイトルを取らずに、インターネット上での売り手と買い手の商売を取り次ぐ」モデルである。このタイトルを取らないというところが鍵である。主催者はタイトルを取らず、商売の取次ぎ時に取り次ぎ手数料を取るだけなので、商売の支払いトラブルやクレームに関しては、商売当事者たちが各自で対応しなければいけなくなる。このことが、Market Placeが普及しなかった大きな原因の一つといえる。 このモデルは、Virtual storeによって起こる「中抜き」への対策として、商社の手によって、プラスチックや鉄などの素材業界ではじめられるものが主流となった。Market Placeは、多対多の構図であるため、1つの強力なMarket Placeが存在すればよい。そのため、各商社が各自で作るのではなく、各社が相乗りしたり、連合したりする形で大きなMarket Placeが作られた。その結果、マネジメント上の主導権がどの会社にあるのかが分からなくなり、そうした混乱もMarket Placeが失敗した要因になった。現在、ほとんどのMarket Placeは収入がない状態であり、大失敗に終わったといえる。 Market Placeは、その他にもさまざまな難しい問題を抱えている。まず、コモディティー性の低い商品を扱う場合、商品の横の比較ができないということがある。たとえば、同じ自動車用鋼板なら、新日鉄の製品でも神戸製鋼の製品でも区別ができないから、Market Place上で区別して比較する必要がないのである。そのため、コモディティー性が高い商品の値段を比べるサイトとしての役割しか果たさなくなってしまう。 それに加え、Market Placeを始めた1999年から2002年初めまでの時期は、デフレが進行した時期と重なっていた。そうした時期に、安い価格をサイトに載せてしまうと市場が崩れてしまうのではないかという危機感を、みんなが持っていた。価格の一人歩きを恐れるため、Market Placeで示される価格が、実際の市場価格よりも高くなるという現象が、ここでも起きてしまった。 Market Placeの唯一の成功している機能は、二級品や在庫品のオークション機能である。メタルサイトというアメリカで成功したとされていたMarket Placeでも、実はこの機能だけが成功していたのである。 Market Placeの取引が難しい点は、取引の内容を標準化することが難しいというところにある。コモディティー性の高い商品であっても、手形の期日、クレームに対する対応の違い、ビジネス上の条件設定といった価格以外の情報を単純に比較することはできない。しかし、Market Place主催者は、こうした違いを取り仕切ることはできない。今後、このモデルが、単純な証券取引所のようなインフラとして生き残る道はあるが、このようなインフラで儲けることはできないだろう。 3. Procurement siteの総括 Procurement siteについては、去年、アリバ社などが「購買サイト元年」などと言って宣伝していたが、私自身は、それはかなり疑問をもっている。 Procurement siteは多対一の形態であり、アリバ、コマースワン、SAP、オラクルのプロキュアメントソフトを利用して、サイトを構築しているのが一般的である。日本では、100社ぐらいの大企業が採用し、アリバが最大のシェアをとっている。 こうしたソフトを使って、Procurement siteを構築する一例をあげると、まず、ソフト代だけで3億から下手すれば5億円程度支払っている事が多い。さらに、日本企業の場合、このソフトを自分たちのワークフローに合わせるためにカスタマイズするので、その代金に5億から10億円かかってしまう。これだけかけて何ができるのかといえば、文房具を買ったり、交通費を精算したりする程度で、先ほど述べた間接資材の購買といったことはできない。なぜ、間接資材の購入ができないのかといえば、サプライヤー側もソフト会社自身も、電子カタログを準備していないからである。また、こうしたソフトの検索能力は限定的なものなので、600万点もある間接資材のなかから必要なものを探し出すというタスクには対応できない。文房具の場合ならば、アスクルが準備しているものでも1万数千点なので、このぐらいからの検索なら何とかできるといったところである。とても製造業向け間接資材をまとめて扱うレベルには達しない。 アメリカで、インターネットを使って間接資材を購入する場合、グレンジャーなどの間接資材販売サイトにパンチアウトやラウンドトリップ(相手のサイトにとんで、商品を検索し、購入すること)するシステムが多く用いられている。しかし、このシステムを使うなら、わざわざProcurement siteを構築する意味がないので、アメリカでもProcurement siteの利点があいまいになっている。 率直に言わせていただくなら、ソフトの売り手やシステムベンダー、コンサルタントがProcurement siteを説明するとき、「業務効率化によるコストダウン」と「集中購買によるコストダウン」を混在させてROI分析を行い、ソフト導入のメリットを宣伝していると思う。本来、購買ソフトができることは、業務の効率化だけであり、集中購買は購買ソフトとは無関係なのである。 本当は購買ソフトを入れなくても集中購買を行うことはできるのに、「うちのソフトを導入すれば、今まで1社からしか買っていなかったものを10社競合させてから買うことができるので、価格が下がりますよ」、「横浜、名古屋、大阪の各工場で、同じ部品を別々の値段で買っていますが、うちのソフトを導入すれば、3工場とも一番安い値段で買えますよ」と説明したりする。ソフト導入とは関係ない効果もROI分析に入れてしまっている。10億〜20億円もするソフトの価値をROI上の効果として示すためには、こうした本来なら関係のない部分まで盛り込まないと説明ができないのだろう。 今後、ソフトの値段が大幅に下がり、ソフトを自社のワークフローにカスタマイズするのではなくワークフローをソフトにあわせられるやり方に変わっていくなら、Procurement siteソフトの効果が発揮できるようになるだろうが、現状のコストで出来る事を考えると短期間で急速な広がりをみせることはないと考えている。 4.住商グレンジャーの戦略(1)ビジネスの展開領域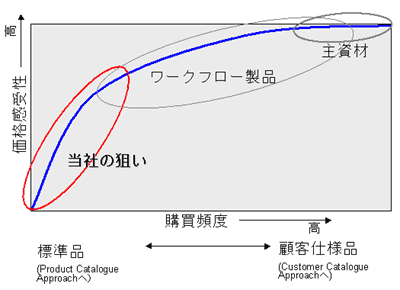 企業で使っているさまざまな資材を、購買頻度と価格感受性の二軸上で分類すると図のようになる。購買頻度の高い資材は、だんだんと顧客仕様化していくと、同時に買い手がその資材についてよく知っているので価格感受性が高くなる。一方、購買頻度の低い資材は、どんな大企業であっても標準品であるし、その財についてよく知らない分、価格感受性は低い。 これまで商社がビジネスしてきた領域は、図中の主資材のところであった。そのため商社が主導したMarket Placeを作る試みでも、この領域でやろうとしていた。しかし、それは失敗に終わった。なぜなら、顧客仕様品が多いため、インターネットの特性と相容れなかったことと、商社がリスクを取らなかったためである。また、価格感受性が高いので、インターネットを導入したところで簡単に価格が下がらなかったことも普及の大きな障害となった。 図中のワークフロー製品とは、よく買っている商品ではあるが、主資材よりも汎用性が高い商品である。アリバやコマースワンは、この領域の商品を電子カタログにしてそれぞれの会社に購買サイトを作らせようとしているのである。これまでに日本で100社程度、米国で1000社程度が導入している。 この購買サイトを動かすためには、電子カタログを作らなければならない。しかし、この電子カタログも、同じ業界であっても、それぞれの顧客に合わせた企業別のものを作らなければならないし、同じ企業内でも、工場別に作らなければいけないこともある。10数万点に及ぶ商品を、何パターンも電子カタログ化していく作業は、非常にコストが高く、無駄である。 このような状況をふまえて、住商グレンジャーのビジネスに関して触れてみよう。われわれは、購買頻度は低いが、大企業でも中小企業でもみんなが標準品を買っている標準品の領域を狙っている。この領域は、買い手の購入価格がバラバラで、大口はとても安いのに、小口の場合はとても高く買わされている。だから、いろいろな価格があるなかで、この程度の価格を示しておけば、ほとんどの人が安いと感じてくれる値段をワンプライスで示している。具体的な取扱商品は、切削工具、作業工具などの工具類、接着剤や潤滑剤などの化学品、機械、機械部品、ボルト、ナット、管工類、文具、保護財、事務家具まで工場で必要な、ほとんどの分野のものである。50万点の取扱商品を載せたワンカタログを用いてビジネスを始めた。 (2)日本の間接資材購入の問題点を突く戦略 サイト経由で、ボールペンを買おうとした場合、もっと安い価格を示す他のサイトがあるかもしれない。しかし、10円安いことよりも、たくさんの業者のなかから選んで購入し、記録をつけ、デリバリーを確認するという一連の作業が、1時間かかるのか5分ですむのかということの問題のほうがよほど重要だと考える。価格以外のところで、魅力的なサイトを作っていく方がより大事だと考えている。 (3)住商グレンジャーの強み 1. 日本最大の商品点数 現在50万点も扱っているサイトはわが社のほかにない。よく比べられるアスクルやコクヨネットは1万数千点である。また、取り扱い範囲も文具限定ではなく、すべての工業資材が入っているところも大きな違いである。 2. テストサイトの経験に裏打ちされた使いやすさ テストサイトを立ち上げ、そこからの経験によって現在のサイトを作っているので、サイトとしての使い勝手が極めてよくなっている。 3. 価格競争力 ITを利用した流通コストの低減とともに商社であるがゆえに、どこから買えば安く買えるのかという知識を持っていた。この2つの点から高い価格競争力を維持している。 4. 価格を明示した紙カタログ、電子カタログ わが社の明示する価格は、売れる値段をワンプライスで示してある。他社のように、リファレンスプライスを示し、実際の値段は別ということはしない。情報が簡単に手に入るというインターネット上のメリットを生かすためには、正確なワンプライスを示すことが大切である。これは、B2Cではやられてきているのに、B2Bではやられてこなかった。ワンプライスだとお客さんに不安も抱かせないし、駆け引きもいらない。信じてもらえるようになれば、うちで購入することは、時間の短縮になるというとが分かってもらえるだろう。 5. 米国グレンジャー社の経験 現在、B2Bで唯一成功しているがグレンジャー社である。その経験を十分に活用できる。 6. 強力な検索機能 50万点の商品から、お客さんが必要なものを見つけ出すためには、検索機能が最も重要である。この機能を強化するために、テンマという新しい検索エンジンを導入する。この検索エンジンは、品番、キーワード、メーカー名、商品属性を組み合わせた検索が行えるので、商品知識がない人でも、過不足なく、すばやく商品に行き着けるようにしている。このエンジンは、今年の10月から導入されるが、ここで大きなビジネス上のステップアップが起きると考えている。 5.B2B eコマースに成功するための4要素米国グレンジャー社との議論の中でもB2Beコマースに成功するためには、以下の4つの要素を必ず実践しなければならないと云う点で我々は合意している。 1.Promotion まず、会社の存在を知ってもらわなければならない。メール8割サイト2割といわれるが、eコマースサイトを作ったところで最初は人がこない。だから、最初はプッシュマーケティングが必要になる。あらゆる手段でサイトを知ってもらわなければならない。わが社の場合、紙のチラシを日本中の製造業の会社50万社に配った。そのうち1万社が顧客登録してくれた。eコマースに関係ないように見えるこうした部分を、しっかり抑えておかないと何も始まらない。 2.Customer Interface 知ってもらった後は、興味をもち、その上で信用してもらわないと買ってもらえない。この信用をどうやって構築していくかがB2Bビジネスの鍵になる。 3.Database & Search 本当の意味でのeコマースの差別化要因は、この要素である。われわれは検索がもっとも大切であると考え、さまざまな改良を加えている。 4. Fulfillment 与信、物流、支払いなどである。地味だが、できて当たり前、できなければ継続ビジネスにはならない要素である。これは、すべてのビジネスに共通するものである。 6.まとめ −B2Beコマースへの期待−最後に、今後のB2Beコマースの行く末についての期待を述べたい。 まず、すぐに何兆ドルビジネスになるという、リサーチ会社やコンサルタントが言っているような話にだまされてはいけない。これらの予想には、単純に、いまあるビジネスをEDIに置き換えたものまでB2Beコマースだとして計算しているものがほとんどである。そうではなく、もっとB2Bビジネスやeコマースの本質について考えなければならない。 B2Bやeコマースの本質とは、情報コストの低減と情報共有を通じた流通コストの低減にあると考える。日本は、いままで流通コストがかかりすぎていた。日本の流通は多重構造になっており、そのことが、一物多価の問題を生む背景になっている。多数の販売店を対象にして交渉力を持っている大企業と、地元の1社しかない小売店からも十分なサービスを受けていない中小企業では、同じ工具を買うのに2倍以上の値段の違いがあるのが現実である。こうした弊害はなくさなければいけない。 しかし、間接資材は取り扱い点数が膨大であるため、誰も情報管理ができないで、これまできてしまった。インターネットのビジネスを通じて、情報を透明化し、誰でも分かりやすく簡単に手に入れられるようにすることで、流通コストを下げたいと考えている。 しかし、こうしたわれわれの動きに対して、「住商グレンジャーに商品を卸すな」という既存流通からの圧力や、独占禁止法に違反するようなことを平気で言ってくる会社がたくさんある。まだそんな状態の業界であるが、不必要な情報統制の結果生まれている多重な流通コストがインターネットの活用によって是正されるなら、一物一価のB2Bが実現できるであろう。 討議コメント:ミスミやアスクルという先行例に見られるように、このタイプのビジネスは失敗しないタイプだということを十分に認識して、ビジネスを始めたように見受けられる。ターゲットにしているのは、企業内個人であり、この人たちは、組織に属していながらも購入の自由裁量の範囲において、各自で御社のユーザーになっている。この個人の部分を十分に認識し、ただのB2Bではなく、B2B(C)という視点で考えなければいけないだろう。Q: ブランド戦略の観点から考えて、ベンチャー企業は自社のモデルやシステムをブランド化していかないといけない。ミスミの「購買代行」やアスクルの「明日くる」は、それ自体がブランド化されたから、うまくいったのである。その観点からすると、住商グレンジャーという名前は良くないのではないか。 A: まず、通販ビジネスの宿命として、相手の顔が見えない分、信用を獲得するのが厳しいという面がある。その意味では、同じ値段である限り、「住商」や「グレンジャー」という名前がもつ信用力が非常に役に立つ。また、アメリカで実績のある「グレンジャー」の名前は、アメリカ駐在のあるメーカーの人にはとても馴染みがあるので、取引の役にも立っていた。この効果は、立ち上げ間もないベンチャーには大きかった。しかし、ご指摘のとおり、いずれ、この名前が邪魔になってしまうのではないかという予感はある。そのため、いま、「Monotaro.com (モノタロウ)」という名前も用いたダブルブランドにしている。いずれこちらの名前にしたいが、今は併用である。サイトでの宣伝はモノタロウを中心にして、こちらの名前が浸透していくことを狙っている。 Q:取引している企業は、どのくらいの規模のところが中心なのか。 A:大企業から中小企業までさまざまである。大企業の場合も、購入額が小さいので、工場の担当者の判断でわが社を利用している。ビジネスを立ち上げた当初、大企業の中間資材を数千万円単位で扱えれば、すぐにビジネスになるなと考えていた。そこで、パイロット時点では、35社が大企業だった。しかし、大企業向けだと、結局、それぞれの会社専用の品揃えで対応しなければならなくなり、非常に大変なことが4ヵ月ぐらいで分かった。そうやって大企業に対応していくより、中小企業に対応していくほうが効果的である。 Q:在庫は持たないのか。また、600万点の間接資材のうちで50万点の取り扱いというのは少ないのではないか。 A: 最初の時点では持っていなかった。しかし、やっているうちに、コアになる回転率の高い商品は持つことにした。それは、まったく持っていない場合、物流センターの入荷と出荷が時間的に重なってしまい、混乱が起きるからだ。また、「注文して、物流センターに納入して、そこから配送するから明後日になる」というと、アスクルの影響がある今日の状況では、不満をもつ顧客もある。だから、注文の頻度の高い1000アイテムほど在庫しており、こうした即納商品を増やしつつある。取扱商品数としては50万点であるが、日本の工場ではほんの少しの違いのさまざまなアイテムを持ちたがるので、それぞれの顧客の使用アイテムのうち20%程度のカバー率だと思う。しかし、顧客仕様の商品や顧客の声を受けた自主開発商品を持って対応するより、標準品を正確にそろえ、次にどのアイテムをそろえるのが良いのかというマーケティングに力を注いでいる。 Q:全体のオーダーのうち、どのくらいがインターネットでなされているのか。 A:半分くらいである。しかし、2回目以降のオーダーは80%がインターネットになる。 Q:瀬戸社長は、ビジネスの構想から現在までビジネスを率いてきた起業家である。一方で、住友商事の子会社の社長というサラリーマンの立場である。なぜ、そうした立場でそこまで頑張れるのか。 A:変な話になるが、正直な話、お金なんかより、自分の考えていることが実現しビジネスになるということがものすごく楽しい。食べていける限りは、いくらでもやると思う。だから、給料が倍になったとしても、この会社から離れるのはいやである。マネジメント・バイ・アウトなどの問題は、いま考えていない。 Q:経営上の意思決定に際して、親会社の住友商事からの圧力はあるのか。 A:この問題は深く考えた問題でもある。しかし、ベンチャーキャピタル(以下VC)と三井物産を出資者として入れる時点で、住友商事とグレンジャーの特殊な拒否権をすべて失わさせた。これができないと、VCは出資してくれない。アメリカのVCが入ったことで、経営の中立性という面では、かなり透明になったといえる。 |











