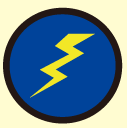消火器の選び方と使い方
消火器の選び方
消火器には加圧式・蓄圧式がありますが、いずれも炎が天井まで到達する程度の火災規模を想定しています。そのためまずは消火器を設置する予定の事務所などにある可燃物に着目し、起こり得る火災の種別と着火物になりそうなものに適した薬剤の消火器を選ぶようにしましょう。
その上でなるべく能力単位の大きいものや、扱いやすいものを選ぶことが大切です。特に密閉された部屋や地下の場合は消火作用以外の特性にも注目してください。
「業務用消火器」とは、設置義務のある場所に設置することができる消火器のことです。6ヶ月ごとの法定点検が必要ですが、耐用年数は8~10年と長く、住宅用消火器よりも消火能力・使用範囲ともに優れています。
まずは業務用消火器の側面に記載してある「火災種別」のマークを確認しましょう。火災種別とは、燃える対象による火災の種類のこと。業務用消火器は、「A火災(普通火災)」「B火災(油火災)」「C火災(電気火災)」の3種に対応します。それぞれ記載の数字が大きいほど消火能力が強いです。
- 【A火災(普通火災)用】

- 適合:木材・衣類(繊維)・紙などの火災
- 能力:A-1からA-10
- 【B火災(油火災)用】

- 適合:灯油・石油などの油の火災
- 能力:B-1からB-20
- 【C火災(電気火災)用】
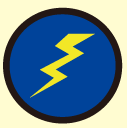
- 適合:変圧器や配電盤など感電の恐れのある電気設備・器具の火災
- 能力:なし(感電の有無を示すのみ)
- 【住宅用消火器】

- 業務用よりも軽くて小さく、女性や高齢者でも簡単に使用することができるので、厨房やコンセント周りなどに追加で設置しておくと良いでしょう。
「消火剤」とは、火を消すために使われる薬剤のことです。消火器に使用されている消火剤は、「粉末」「ガス」「水」の3種類に大別されます。それぞれ「消火能力が高い」「汚染が少ない」など特長があるので、使用箇所に合わせて選ぶと良いでしょう。
- 【粉末または中性強化液】
- 最もスタンダードな消火剤で、幅広い火災種別に対応します。放射時間は短めですが消火能力が高く、即効で火の勢いを抑え込むことが可能です。特に中性強化液タイプは浸透性・再燃抑制効果共に高い点が特徴。ただしいずれも薬剤による汚損が激しいというデメリットもあります。
- 適合火災:A・B・C
- 【二酸化炭素】
- 窒息作用で消火するタイプです。ガスなので対象物の汚染がなく、電気設備や精密機械、博物館などの設置に向いています。ただし狭い密室や地下街では窒息する危険があるため、使用することはできません。レバーを離すことで放射が止まるため、少しずつ利用することが可能です。
- 適合火災:B・C
- 【水】
- 水が主成分の消火器で、冷却効果・浸透性が共に高いという特長があります。埃・塵・化学物質で汚したくないクリーンルームなどにおすすめです。放射時間が比較的長いので、落ち着いて消火活動にあたることができます。
- 適合火災:A・C
消火器の使い方
では、具体的にどうやって消火器を使えば良いのでしょうか。いざという時に素早く適切な対応を取れるように、あらかじめ頭に入れておきましょう。消火器によって扱い方が異なりますが、基本的な使い方についてこちらでご紹介します。
火元からある程度の位置に消火器を安全に運びましょう。この時、あまり離れすぎると火に届く前に消火剤が尽きてしまいます。消火器にもよりますが大体7~8m手前を目安にしましょう。また屋外の場合は、安全性を考慮して必ず風上に回ってください。 室内の場合は出入口を背にすること。一本ではなく、十分な本数で一斉に放射するようにしましょう。位置に着いたら、レバーに付いている黄色い安全栓を引き抜きます。
ホースを外し、そのノズルを持って火元に向けます。この時ホースの根元を持つと狙いが定まらないので、必ず先端を持つようにしましょう。消火器が重ければ無理に持ち上げなくても、地面に置いたままでも構いません。
片方の手でノズルを持ったままもう片方の手でレバーを強く握ると、消火剤が放射されます。粉末消火器の場合は15秒程度で放射しきるので、しっかりと火の根元を狙いましょう。手前からほうきで掃くように放射することがポイントです。
一度消えたと思っても再燃焼する恐れがあるため、念入りに放射してください。
いざという時に人の命はもちろん建物・設備を守る消火器は、あらゆる事業者にとって非常に重要なものです。適切な消火器を選定した後は、落下する恐れがなく、高温にならず、雨風に晒されない安全かつサッと持ち出せる場所に設置しておきましょう。